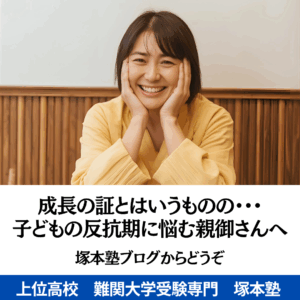「やる気」は後から湧く——東大・脳科学者に学ぶ、今すぐ実行できる勉強習慣とスマホ対策
「うちの子、やる気が出ないんです・・・」
親御さんから最もよくいただくご相談です。ですが、実は“やる気”というのは待っていても降ってくるものではないようです。
脳科学の研究によれば、やる気は「行動の結果」として後から生まれるものだそうです。つまり、動き出してしまえば脳がスイッチを入れてくれるのです。
今回は東大・池谷裕二教授の論を手がかりに、
「やる気が出ないときにどうすればいいか」
「集中力を高める方法」
「やってはいけないこと(特にスマホ対策)」
について、塾長・塚本の経験を交えてわかりやすくお伝えします。
塾生の80%以上が、堀川・西京・桃山・城南菱創以上に合格する
上位校受験専門塚本塾のインスタグラム
行動が先、やる気は後——「作業興奮」を親子で起こすコツ
「やる気が出ないからできない」という声は、勉強に限らず日常でもよくあります。
しかし脳科学では、やる気は行動を起こした“後”に湧いてくるとされています。この現象を「作業興奮」と呼ぶそうです。
たとえば、部屋の片づけ。
最初は重い腰が上がらなくても、一度手を動かし始めると「あれも片づけよう」と次々進んでしまう経験はありませんか? 勉強もこれと似たようなところがあります。まず小さな一歩を踏み出せば、脳が「よし、続けよう」と働き始めるのです。
親御さんも協力できる工夫として、こんなんはいかがでしょうか。
- 「5秒ルール」で即行動
思い立ったら5秒以内に机へ。迷う時間を作らないのがコツです。 - 体を動かすことから始める
鉛筆を削る、机を拭く、椅子に座る。こうした小さな行動でもスイッチは入ります。 - 場所を変える
リビングや図書館など、環境を変えることで「やらざるを得ない」雰囲気を作れます。 - 小さなご褒美を設定
「5分やったらシール」「1ページでおやつ」など、小さな達成感を積み重ねると継続しやすいです。 - なりきり効果を活用
「今日は科学者になったつもりで理科をやろう」といった遊び心も効果的です。
池谷教授によると、こういうのを、「システムに身を置く」というそうです。
できる人は、やる気を出そうと頑張るのではなく、余計なことを考えずにシステムに従う人だとおっしゃっています。
要するに大切なのは、「やる気を待たずに行動する」こと。
親御さんが一言「とりあえずテキストを開いてみよう」と声をかけるだけで、流れは大きく変わります。
集中力を底上げする学び方——「15分×3+休憩」の設計と生活リズム
集中力はそんなに長く続くものではありません。人間の脳は、数十分で疲れてしまうようにできています。
ですから「だらだら2時間」より「短時間×複数回」の方が効率的です。
長時間の勉強に慣れていない人や、勉強初心者の人へのおすすめは、
「15分×3+休憩」という学習法です。
- 15分集中を3回繰り返す
最初はウォーミングアップ、2回目にピークが来て、3回目でまとめ。
合計45分の勉強時間ができます。 - その後は必ず休憩
5〜10分の小休止を入れると、脳がリセットされて次の学習が効率的に。 - 記憶の定着が高まる
研究でも、短い集中を繰り返す方が翌日・1週間後の定着率が高いことが示されています。
勉強の効果を上げるには、生活リズムの安定が欠かせません。睡眠不足の状態では、どんな勉強法も効果を発揮しにくいのです。
親御さんができることは、
- 睡眠を多くとらせて、就寝・起床時間を一定にさせる
- 朝ごはんでエネルギーを補給させる
- 勉強時間を毎日同じ時間帯に設定する
こうした習慣が「この時間は勉強するもの」という体内リズムを作り、集中が持続しやすくなります。
やる気が出ない日の具体レシピ——環境・行動・ご褒美・締め切りの“微調整”で前進する
誰にでも「今日は乗らないな」という日はあると思います。そんな日は「ゼロにしない」ことを目標にしましょう。
少しでも進めば、その達成感が次につながります。
具体策としては次の4つです。
- 環境を変える
机でダメなら床に座ってもできます。天候が許せば外でもOK。場所を変えると新鮮な気持ちになります。 - 行動を変える
順番を変えてみるのも効果的。普段は国語からなら、今日は理科の図を描くことから始めてみる。 - 小さなご褒美を設定
「1ページ解いたら音楽を1曲」「終わったらおやつタイム」など、日常的な楽しみがやる気を後押しします。 - 短い締め切りを作る
「夕飯までに」「お風呂の前に」など、時間を区切ると集中しやすくなります。
こうした“微調整”が、やる気が出ない日でも一歩を踏み出させてくれるものですよ。
やってはいけないことリスト——スマホは“近くに置かない”が鉄則
最後に「やる気と集中を妨げるもの」に触れておきましょう。現代の中高生の(小学生もか)最大の敵はスマホです。
- 机の上にあるだけで注意がそれる
使っていなくても、視界にあるだけで脳は気を取られます。 - 通知のオンは絶対NG
1回通知が鳴ると、元の作業に戻るまで平均20分かかると報告されています。 - マルチタスクは効率を下げる
「音楽を聴きながら」「LINEをしながら」の勉強は効率半減。脳は同時処理できません。 - ながら見は危険
テレビや動画を流しっぱなしでは学習内容が頭に入りません。脳のリソースをそこにはかけられません。
ですから勉強中は、
スマホを親に預ける
別の部屋に置く
通知をオフにする
この3つが鉄則です。そして勉強が終わってからのんびりと使う。このメリハリこそが集中力を守る秘訣です。
まとめ
やる気は「行動の後」に生まれる。だからこそ、最初の一歩を踏み出す工夫が大切です。
そして「短時間集中+休憩」で効率を高め、やる気が出ない日には環境や行動を微調整する。
さらに、スマホを遠ざけることで集中を守る。
親御さんがこうした事柄を理解して声をかけてあげると、お子さんは「やる気を待つ子」から「行動できる子」へと変わっていきます。
やる気はプレゼントのように降ってくるものではなく、行動の副産物としてついてくるもの。今日から少しずつ実践してみてください。
参考文献
池谷裕二『受験脳の作り方―脳科学で考える効率的学習法』新潮文庫、2011年.
※脳科学の視点から、記憶の仕組みと勉強法をやさしく解説。親子で読める一冊。
池谷裕二『自分の脳を自分で育てる』講談社ブルーバックス、2017年.
※やる気や集中力に関する脳の働きを、日常生活と結びつけて紹介。
茂木健一郎『脳を活かす勉強法』PHP新書、2007年.
※脳科学を基盤にした勉強のコツを、中高生にもわかりやすく解説。
佐々木正悟『ついスマホを見てしまう人のための集中力が続く心理学』ダイヤモンド社、2020年.
※スマホとの付き合い方や集中力低下の仕組みを、わかりやすい言葉で解説。