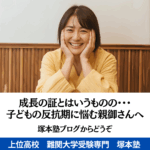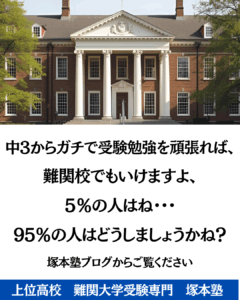保護者説明会 「わが子の国語力…
勉強ができる子に育つのは机の上ではなく、小学4年生からの世の中経験で決まる
「勉強ができる子に育てたい」
あるいは、そこまでではなくとも、
「勉強できるにこしたことはない」
親なら誰もが願うことでしょう。しかし、その思いが空回りしていませんか?ドリルや参考書に追われるものの、休日はショッピングモールで時間を潰すだけ。
そんな家庭から、未来を担うリーダーが生まれると思いますか?
実は、小学4年生から中学生になるまでの数年間こそが、子どもの学力を決定づける“ゴールデンタイム”。
鉛筆を握っての「勉強」を始める前に、勝負はすでについているのです。
机上の勉強よりも、世の中を知る経験が子どもを突き抜けさせます。
今回ここで書くことは、塾長・塚本が実際に生徒たちを見てきた中での、そして子育てをしてきた中での肌感覚にすぎません。
統計的な真理でも文部科学省の公式見解でもなく、あくまでも一人の教育現場の人間の実感です。それでも「なるほど」と思ってくれる人がひとりでもいればと思い、書いてみます。
塾生の80%以上が、堀川・西京・桃山・城南菱創以上に合格する
上位校受験専門塚本塾のインスタグラム
鉛筆を持つ前に勝負はついている──「勉強ができる子」の決定要因とは
「勉強ができる子は、生まれつき頭がいいから」
そう思い込んでいる親御さんは多いかもしれません。けれども、それは大きな誤解です。
私が塾長として長年子どもたちを見てきて、また、自分の子育てを経験して痛感しているのは、
わずか10年ほどしか生きていない子どもたちそれぞれの間に、すでに圧倒的な差がついているという、驚くべき事実です。
つまり、鉛筆を持つ前に、すでに勝負はついているということです。
小学校低学年までは、勉強といっても計算や漢字など、反復すれば誰でもできる「作業」が中心です。
しかし小学4年生くらいから、内容は一気に抽象的になります。「考える」ことが増えるのです。
国語は説明文を読み解く力、理科や社会は因果関係を整理する力、算数は文章題を式に落とし込む力が必要になります。
ここでモノを言うのが「経験」です。
川で遊んだことのある子は流れの性質をすぐ理解できるし、美術館に行った子は「最後の晩餐」と聞いて、あっ、あれか!と具体的にイメージできる。
逆に、休日をゲームと買い物だけで過ごしてきた子は、頭の中に素材がないから理解が空回りする。
これは私の肌感覚だけではなく、いくつかの研究でも裏づけられています。
国立情報学研究所の新井紀子氏の調査では、教科書の文章を理解できない中学生が多数存在することが明らかになりました。背景知識がなければ、そもそも文章を読んでも意味がわからないのです。
さらに、海外の大学の研究でも、小学生のときに博物館や美術館に触れた子は、その後の読解力や創造性が高まると報告されています。
つまり、経験の差がそのまま学力の差になるのです。
小学4年生から中学生前までが“ゴールデンタイム”の理由
では、なぜ「小学4年生から中学生前まで」が特別なのでしょうか。
私が勝手にこの時期を「ゴールデンタイム」と呼んでいるのですが・・・
理由の一つは、言葉の発達と文字(漢字)の習得です。
9〜10歳ごろは、個人差はありますが、具体的な事象をもとに抽象的に考える力が急速に伸びる時期。
言葉を得ることで抽象的な事柄について話したり、想像したりしやすくなります。
また、言葉や漢字の習得量が増えてきて、世の中にあふれる文字情報を取り込める場面が増えてきます。だから、この時期に経験を与えれば、知識が点から線へとつながり始めるのです。
もう一つの理由は、「中学生になった途端の忙しさ」。
部活動、定期テスト、友人関係など、中学に入ると、子どもたちはあっという間に時間を奪われます。
小学生の時のようにのんびり読書や博物館に行く余裕や、親子でゆっくり会話をする時間すらほとんどなくなる。
だからこそ、その前の数年間が勝負なのです。
現場で見ても、個人差は歴然です。
休日に科学館や自然公園に行っていた子は、中学に入っても理科の課題に食らいつける。一方で、休日をゲームで過ごしてきた子は、教科書の基礎用語を覚えるだけで手一杯。
才能やIQではなく、「ゴールデンタイムをどう過ごしたか」の違いなのです。
国際的な学力調査であるPISAのデータも同じようなことを示しています。
読書習慣や文化施設に触れる経験のある子は、数学的思考力や読解力で顕著に高い得点を出すのです。
机に向かうより大切な「経験値の積み上げ」こそ最強の投資
「毎日ドリルをやらせています」
「宿題は欠かさずやっています」
親御さんからよく聞く言葉です。
しかし、その努力が報われない子が多いのも事実です。
原因は単純で、経験値が不足しているからです。
歴史で「城下町」を習うとき、実際に城跡や旧跡を歩いたことがある子は一瞬で理解できます。
理科で「外骨格」と習ったとき、カニを捕まえたり、昆虫を観察した経験がある子はイメージできます。
経験のない子は、黒い文字をただ暗記するしかありません。
教育心理学の知見では、学びは「既有知識との関連づけ」で定着するとされます。
経験は知識を意味づけ、深く根づかせる。だから経験を獲得しに行くことは余暇ではなく、親が子どもにすべき最強の投資です。
実際、学校で行われる全国学力調査でも、家庭で多様な経験をしている子の正答率は明らかに高いと感じませんか。
机に向かう時間も大事ですが、それ以上に経験の積み上げが学力の燃料になるのです。燃料なしにアクセルを踏んでも、車は走りません。
親が選ぶ休日の過ごし方が子どもの未来を分ける
最後に、親御さんに最も伝えたいのはここです。
休日の過ごし方が、子どもの未来を決める。
そんなたいそうな、と思われるかもしれませんが・・・
休日を「とりあえず近所のイオン」で終える家庭から、将来のトップランナーはほぼ育ちません。
もちろんショッピングモールが悪いわけではありませんが、そこには学びの要素はほとんどないので。
小4〜中学入学前までのゴールデンタイムを消費で終えるのか、経験として積み上げるのか、大げさではなく、その選択が未来を分けます。
休日は経験値を稼ぐ日と位置づけましょう。
科学館、美術館、歴史ある寺社仏閣、自然公園、図鑑を片手にした地域探検などなど。
余談ですが私自身、夏休みや年末年始、GWなどの長期のお出かけの際には、入念に下調べをして、6~7時間をかけて行程表を作りました。
教科書に出てくる有名な場所を、片っ端から巡ってみたり。
わざわざ白河の関まで行ってみたものの、えっ?これだけ?ってなったこともありました笑
それでもこれらはすべて、後々の子どもの勉強を支える「勉強体力」になったと確信しています。そして、その体力を子どもに与えられるのは親だけなのです。
子どもは自分で世界を選べません。親が見せる世界しか知ることができない。
だからこそ、親の覚悟が、子どもの未来の選択肢を広げるか閉ざすかを決めるのです。
おわりに
今回述べてきたことは、塾長・塚本が子育てと教育現場で実感した「肌感覚」にすぎません。
それでも、私は断言します。
勉強ができる子に育つかどうかは、机に向かう前の経験によってすでに決まっている。
そしてその経験を与えられるのは、他ならぬ親御さんなのです。