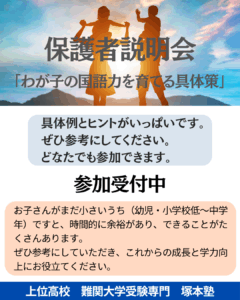京都府上位高「堀川・嵯峨野・西…
本当に伸びる子は「能動的な勉強」をする──親と塾が見守る自立の一歩
受験生をお子さんに持つ、あるいはお子さんが受験生だった親御さんにお聞きします。
「最近はどんな勉強をしてるん?」「今日は何を勉強するの?」と尋ねた時に「分からない」と答える。そんな場面に出会ったことはありませんか。
これは実は、学力よりも大切な「自分で考える力」が十分に育っていないことの現れかもしれません。
勉強を通して身につけてほしい力は、テストで点を取る力はもちろんですが、究極的には自分の頭で考え、選び、行動する力です。それが高校入試や大学受験、そして将来の社会生活において大きな支えとなります。
塾生の80%以上が、堀川・西京・桃山・城南菱創以上に合格する
上位校受験専門塚本塾のインスタグラム
受け身の勉強を続けるとどうなるのか
小中学生のうちの勉強は、親や先生のサポートがあるほうが、多くの子にとってよいかもしれません。
特に小学生のうちは、宿題の声かけや時間の管理など、周りの助けがあるほうが、より勉強習慣が根づきやすいでしょう。ですが、学年が上がるにつれて、少しずつでも自分で決める力を育てていくことが大事になってきます。
そして、中3になっても「何を勉強したらいいか分からない」と言ってしまう状態は、やはりまずいです。
受験勉強は待ってくれませんし、先生や親が代わりに戦ってあげることもできません。結局、試験本番で答案用紙に向き合うのはお子さん自身です。
その時に頼れるのは、自分で考え、自分で判断し、自分で取り組んできた経験だけです。
勉強は、言われたことだけをやっているうちは、実は楽なものです。しかし、そのやり方だけでは、遠からず必ず限界が来ます。
誰かに指示されないと動けないままでいると、課題に直面したときに立ち止まってしまいます。
いっぽう、「自分は今日はここをやるんだ」と主体的に決められる子は、迷ったとしても自分で軌道修正ができるのです。
一方通行の授業では「考える力」が育ちにくい
多くの塾が採用している講義形式の授業は、一見すると分かりやすく、親御さんにとっても安心感があります。
「先生がしっかり教えてくれているから大丈夫」と思えるからです。
けれども、その安心感の裏側に落とし穴があります。子どもにとっては、与えられた内容をこなすだけの“受け身の学び”になりがちだからです。
「今日はこの単元をやります」と先生が言い、生徒はその通りに進める。確かに素晴らしく効率的ではありますが、実は自分で学びを選ぶ経験がほとんどないまま時が過ぎてしまいます。
そういう私もかつては大手塾や中堅塾の教室長を務めて、たくさんの集団授業を担当していました。
1日たりとも隙がなく作られた、完璧なカリキュラムの下で、華麗なる授業?(笑)を日々行っていました。いや~、自己満足でしたね・・・
もちろん、生徒が「何を勉強するか」を考えて選ぶ余地など1ミリもありません。
考える余地がない代わりに、高校に合格するためというその一点においてだけは、素晴らしいカリキュラムです。
高校に合格するという、ただその一点のみにおいては、です。
ただしその後のこと、そこから続く高校での勉強や大学受験のことは知らんがな、でした。
今思い出しても、あの頃の生徒たちには、その点については「ごめんな」と思います。
もちろん、自分で塾をやっている今では、その点においての考えは180度変わっています。
いや、考えが変わったことが、塾を開いた原点になっているので、
だから今はこんな塾をやっているんです。
話がちょっと逸れてしまいました。
何がお伝えしたかったかというと、高校入試はもちろん、その先の大学入試でも、「自分で弱点を把握し、何をどう勉強するかを考える力」が不可欠だということです。
ところが、一方通行の授業に慣れた子は、その場を離れると学び方が分からなくなってしまうことが多いのです。
実際に、高校受験専門の塾に通っていて、高校生から塚本塾に入ってきた生徒が、
学習計画を立てて実践することに苦労するケースが少なからずあります。
「考える力」を育てるには、先生が全てを決めるのではなく、生徒自身に選ばせる場面が必要です。
どんなに小さな選択でも、「自分で決めて進めた」という積み重ねが、将来大きな自信につながります。
親がやり過ぎると子どもの自立心を奪ってしまう
もうひとつ気をつけたいのが、親御さんの関わり方です。
「宿題はやったん?」「計画通り進んでる?」と声をかけるのは大切ですが、親が細かく先回りしすぎると、かえって子どもの考える力を弱めてしまうことがあります。
例えば、学習計画をすべて親が作ってしまうと、子どもは「決めるのはお母さん/お父さんだから、自分は言われた通りにすればいい」と思うようになります。
すると、「どう勉強すればいいか分からない」という言葉が口ぐせになってしまうのです。
もちろん、全てを放任すれば良いということではありません。
親御さんの役割は、あくまでサポート役。子どもが自分で考えて立てた計画を一緒に確認してあげたり、迷っているときにヒントを与えてあげたりすることです。
過干渉ではなく、“伴走者”として見守る姿勢が、子どもの自立を大きく育てます。
これから問われるのは「能動的に学ぶ力」
勉強で伸びていく子どもたちには共通点があります。それは「自分で決めて、自分で進めることができる」という点です。
「今日はここをやろう」「テストまでにこの範囲を仕上げよう」と、自分の考えで学習を組み立てられる子は、多少の失敗があっても立ち直るのが早いのです。
なぜなら、それは自分で選んだ課題だから、ですね。人から押しつけられたものではなく、自分自身の意思で取り組んでいるからこそ、真剣さも継続力も違ってきます。
親も塾も、本来は子どもが能動的に学ぶ姿勢を支える存在であるべきです。大切なのは「やらせること」ではなく「やれるようにしてあげること」です。
自分で考えた勉強に取り組めるように環境を整え、必要に応じてそっと支える。そうした関わりが、受験を乗り越える力を育み、将来の学びにつながります。
「自分で考え、自分で選び、自分で行動する」。
これは勉強だけでなく、人生そのものを切り拓いていくうえで欠かせない力です。今日の小さな一歩を、これからのお子さんの大きな成長につなげていきましょう。