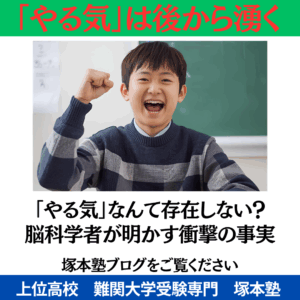京都府上位高「堀川・嵯峨野・西…
反抗期は悪いこと?30年の経験を基に塾長が語る“自我の芽生え”と、親子関係を前向きに乗り越えるヒント
小学生や中学生を育てる親御さんにとって、「反抗期」という言葉はどうしても不安を伴うものです。
子どもが言うことを聞かなくなる、口ごたえが増える、勉強や生活態度でぶつかる…。そんな時期を前に、「どう接すれば良いのか?」と悩まれる方も多いでしょう。
私は塾長として、これまで多くのご家庭や生徒と向き合ってきました。その中で感じるのは、反抗期は決して“悪いもの”ではないということです。むしろ「自我の芽生え」が育っている証拠であり、子どもが自立していくための自然なプロセスなのです。
今回は、親御さんに知っていただきたい反抗期の本質と、その乗り越え方について経験を交えてお伝えします。
塾生の80%以上が、堀川・西京・桃山・城南菱創以上に合格する
上位校受験専門塚本塾のインスタグラム
自我の芽生えとは?反抗期の正体を塾長の視点で解説
「うちの子、そろそろ反抗期かもしれない…」
そう感じるとき、多くの親御さんは「厄介な時期が来た」と構えてしまうものです。しかし、私の経験から言えば、反抗期は決して“悪者”ではありません。
私は塾で長年、多くの生徒たちと接してきました。また、我が子もまさに反抗期の真っ只中のど真ん中です笑
その中で見えてきたのは、反抗期とは「自我の芽生え」にほかならないということです。言い換えれば、「自分なりの方法を確立したい」という子どもの強い欲求です。
幼いころは、食べ方・遊び方・友達との関わり方など、生活の細かいこと一つ一つで「自分流」を試そうとします。
やがて中学生、高校生になると、その対象は「進路」「友人関係」「一日の過ごし方」といった人生そのものに広がっていきます。
つまり反抗期とは、
「自分のやり方を見つけたい」「親のやり方と違ってもいい」という意思表示なのです。
年齢・学年で変わる「方法論の衝突」と親のかかわり方
幼児期から小学生のうちは、身近な生活習慣をめぐる衝突が目立ちます。たとえば、
- 「早く準備しなさい!」
- 「宿題を先にやりなさい!」
親が当然と考えてかける言葉も、子どもにとっては「自分のペースを乱された」と感じるものです。
子どもが「うるさい!」と返すのは、単に反抗しているのではなく「自分の方法を試したいから口出ししないで」というサインなのです。
そして中高生になると、衝突はより大きなテーマに広がります。
- 「進路をどう選ぶか」
- 「友達とどう付き合うか」
- 「将来どんな生き方をしたいか」
これはまさに「人生の方法論」をめぐる衝突です。
親から見れば、「もっとこうすればいいのに」と子どものためを思って声をかけ、アドバイスします。一方で、子どもは自分の視点で人生を模索しています。
ここで大事なのは、親の価値観を押し付けすぎず、子どもの考えを一度受け止める姿勢です。
私自身の場合は、
「お父さんも昔、実は14歳やったことがあるからな、気持ちはわかるで~。」
と、共感を示す言葉をかけるようにしています。
親御さんにも14歳の時期があったことは当たり前ですが、子ども自身には、そういう視点が意外とないですよね。
親御さんも、同じ年頃の頃に、同じような気持ちになったことがあるよというのは、
子どもには新鮮なようです。
価値観は親子で異なるのが当たり前。だからこそ大切なこと
当たり前のことですが、親子は似ている部分がたくさんあります。顔つきや声のトーン、あるいはちょっとした仕草。
しかし、それ以外の多くは実は、「まったくの別人格」です。性格・趣味・考え方・能力は当然違います。
にもかかわらず、親御さんが「自分のやり方が正しい」と強く押し付けると、必ずどこかで摩擦が生じます。軽ければ口げんかで済みますが、深刻になると、心の距離が広がったり、家出などの大きな問題につながったりすることもあります。
私はこれまで多くの親子関係を見てきましたが、親が「子どもは別人格だ」と理解して割り切っているご家庭ほど、関係は穏やかです。
腹が立つ場面があっても、「価値観が違って当たり前」と思うことで、気持ちの切り替えも早くなるのです。
反抗期がない子も危険?健全な自立を育てるための親の姿勢
時々、「うちの子は反抗期がなかった」という話を耳にします。
これについては私は、大きく三つのケースに分かれると考えます。
- 親と子の価値観が偶然一致している場合
この場合はラッキーです。親の意見に素直に共感できるので、衝突の必要がありません。 - 子どもが最初から親の言うことを聞く気がない場合
こういう子は親に干渉されることなく、自分の道を歩んでいきます。
自立が早いタイプとも言えますね。 - もっとも危険なのは「考える力が育っていない場合」
過保護や過干渉によって、子どもが「これは良いのか悪いのか」を自分で判断しなくなっているケースです。
一見素直で手のかからない子に見えますが、実際には「考える習慣がない」「考える必要があるとさえ思っていない」という怖さを抱えています。
私はこの3番目のケースを一番心配しています。
考えることをしないまま大人になってしまうと、自分の人生を自分で選べず、誰かに流されてしまうからです。
だからこそ、多少口げんかになっても「自分の意見を持ち、ぶつけられる子ども」に育てることが大切だと考えています。
反抗期はそのための大事なステップ。親御さんにとっては辛抱の時期ですが、「健全な自我が育っている証拠」と前向きに捉えていきましょう!
まとめ
反抗期とは「自我の芽生え」であり、子どもが自立への階段を登り始めた証拠です。小学生の頃は身近な生活習慣について、
そして子どもが中高生になると人生の過ごし方について、親子は衝突します。ですが、それは子どもが成長しているからこそ起こること。
大切なのは、「親子は全くの別人格」「価値観が違うのは当然」という視点を持つこと。
そして、たとえ反抗的な態度を見せても、そこは何十年と多めに生きている人生の先輩の余裕を見せて、「考える力が育っている証拠」と受け止めることです。
一般の方より、少しだけ多くの反抗期事情を見てきた塾長として、これは確かだと言えます。
反抗期を前向きに捉えられる親御さんの子どもは、必ず自分の人生を自分で切り拓いていけるようになりますよ。