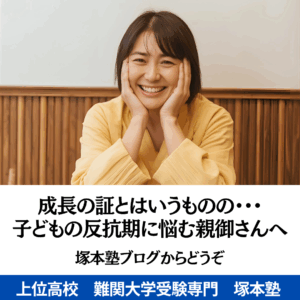京都府上位高「堀川・嵯峨野・西…
親子で取り組む!小学生・中学生の読書感想文がスラスラ書ける書き方のコツ
読書感想文の季節がやって来ましたね。どう進めたらいいのか不安ではありませんか?
「何を書けばいいの?」と悩むお子さんのために、構成の基本から学年別のポイントまで、親としてできるサポート方法をやさしく解説します。
親子で一緒に楽しく進められるヒントをたっぷりご紹介しますので、感想文を「できた!」に変えていきましょう。
塾生の80%以上が、堀川・西京・桃山・城南菱創以上に合格する
上位校受験専門塚本塾のインスタグラム
読書感想文の基本構成を知ろう
お子さんが読書感想文に取り組むとき、「何から書けばいいの?」と悩むことが多いですよね。そんな時は、まず読書感想文の基本の流れを一緒に確認してみましょう。
実は、読書感想文には大まかな“型”があります。この型に沿って書くと、初めてでも書きやすくなりますし、迷わず進めやすくなります。
基本の構成は、
【はじめ】
【あらすじ】
【感想】
【まとめ】
の4つのパートに分かれています。
最初の「はじめ」では、その本を選んだ理由や、本を読む前の気持ちなどを書きます。
たとえば、
「夏休みの課題で選びました」
「友だちにすすめられて読んでみたくなりました」
といった、きっかけを素直に書くとよいです。
次に「あらすじ」では、物語の内容を簡単にまとめます。
すべてを書こうとすると大変なので、
「主人公がどんなことを経験し、考え、悩み、どう変わっていったか」
を中心に、短く紹介しましょう。ここは長くなりすぎないようにすることがポイントです。
そして「感想」が一番大切な部分です。
本を読んで心に残ったことや、「自分ならどう思うかな?」と感じたことなど、素直な気持ちをまとめてみましょう。たとえば「この場面でドキドキした」「登場人物に共感した」など、お子さん自身の言葉で書ければOKです。
最後に「まとめ」のパートです。
読書を通して自分が感じたことや、これからやってみたいこと、本から学んだことなどを、ひとことで表すように書くとすっきりまとまります。
読書感想文は、決して難しい文章でなくても大丈夫。
この4つの流れをお子さんと一緒に確認しながら、まずは「書けた!」という達成感を味わえるように応援してあげてくださいね。
学年別の書き方のポイント(低学年〜高学年)
低学年(1・2年生)の場合
低学年のお子さんは、まだたくさんの文章を書くことに慣れていないことが多いです。
無理に長い文を書かせようとせず、「感じたこと」を短い言葉で書ければ十分です。
たとえば、「ここが楽しかった」「この登場人物が好き」など、素直な気持ちを一言ずつ書いてみましょう。
親御さんが「どこがいちばんおもしろかった?」と質問してあげると、お子さんも自分のことばで答えやすくなります。
中学年(3・4年生)の場合
中学年になると、少しずつ自分の考えや感想を文章で表現できるようになってきます。
この学年ぐらいですと、物語の中で気になった場面や、自分だったらどうするか、登場人物の気持ちを想像してみるのもおすすめです。
たとえば、「自分だったらこんなときどうするかな?」と問いかけたり、「この場面で主人公はどんな気持ちだったのかな?」と想像してみたりすると、感想に深みが出てきます。
親御さんは、答えを急がせず、ゆっくりお話を聞いてあげることがポイントです。
高学年(5・6年生)の場合
高学年になると、文章の量も増え、より自分の考えや経験と結びつけた感想文を書く力が求められてきます。
本の内容と自分の生活や体験をつなげて、「自分も似た経験をしたことがある」「主人公の考え方に共感した」など、具体的に書けるとぐんとレベルアップします。
また、「なぜそう思ったのか」「この本から何を学んだのか」を一緒に考えてみると、より深い感想が書けます。
お子さんが自分で気づきをまとめられるよう、見守ってあげてください。
お子さんの学年や成長に合わせて、無理なく取り組めることがいちばん大切です。「どんなことを書いたらいいの?」と迷ったときは、一緒に本についておしゃべりしてみてください。
会話の中から、お子さんだけの“感想文のタネ”がきっと見つかりますよ。
子どもの「感想」を引き出す声かけのコツ
読書感想文で一番困るのが、「何を書けばいいのか分からない」というお子さんの声ですよね。実は、いきなり「感想を書いてごらん」と言っても、子どもは戸惑ってしまうことが多いんです。
そんな時は、親御さんが少し工夫して声をかけてあげることで、お子さんの中に眠っている思いや考えが自然と引き出されやすくなります。
まずおすすめなのは、お子さんが本を読み終えた後に、「どの場面がいちばん心に残った?」や「どの登場人物が好きだった?」といった、答えやすい質問から始めることです。難しく考えず、会話の延長線上で本の話題を振ってあげると、お子さんも自然に自分の感じたことを話しやすくなります。
さらに、「その場面でどんな気持ちになった?」や「もし自分だったらどうすると思う?」と、少し踏み込んだ質問も効果的です。お子さんが迷っているときは、親御さんが自分の感じたことを少し伝えてみてもいいですね。「お母さん(お父さん)なら、ここでドキドキしちゃうな」など、親の感情をシェアすることで、お子さんも自分の気持ちに気づきやすくなります。
また、お子さんの言葉を否定しないことも大切なポイントです。「それは違うんじゃない?」などとすぐに訂正せず、「そう思ったんだね」と一度受け止めてあげてください。安心できる雰囲気の中でこそ、本音の感想が出てくるものです。
こうした声かけを重ねていくことで、お子さん自身の中にある素直な感想や発見がどんどん言葉になっていきます。親御さんが聞き役にまわりながら、焦らずゆっくり話を聞いてあげることで、読書感想文の“種”が自然に育っていきますよ。
下書きを本番へつなげるチェックポイント
読書感想文の下書きが書けたら、いよいよ本番へと仕上げていく段階です。ここでの親御さんのちょっとしたサポートが、お子さんの自信につながります。
せっかく書いた感想文がもっとよく伝わるように、仕上げのチェックポイントをいくつかご紹介します。
まずは「文章の流れ」をお子さんと一緒に確認してみましょう。
話が途中で飛んでいないか、順番が前後していないかを見直すだけでも、ぐっと読みやすい感想文になります。「このあとに何が書いてあると分かりやすいかな?」と優しく声をかけてあげるのがおすすめです。
次に「言葉の使い方」や「漢字・送りがな」などの細かい部分もチェックしてあげるとよいですね。
全部を親御さんが直してしまうのではなく、「ここはもう一度見てみようか」と促してあげることで、お子さん自身が気づきを得やすくなります。間違いを見つけたときも、「ここがちょっと惜しいね、一緒に考えてみよう」と励ましてあげると、前向きな気持ちで取り組めます。
また、段落ごとの長さにも気を配ってみましょう。
ひとつの段落が長くなりすぎていないか、読み手が疲れない構成になっているかも大切なポイントです。時には声に出して読んでみると、分かりやすさや読みやすさが実感できます。
最後に、「誰かに読んでもらう」という気持ちで仕上げることも大事です。
親御さんが「完成したら読ませてほしいなあ」と声をかけてあげると、お子さんもやる気が湧いてきます。自分の気持ちや考えを大切に、最後まで自分らしい感想文になるよう見守ってあげてください。
親御さんのあたたかいサポートが、お子さんの「できた!」という達成感につながります。ぜひ一緒に、感想文づくりの仕上げ時間を楽しんでくださいね。